まもなく六月。中高生の制服も一斉に夏服へ衣替えですね。だけど最近は移行期間なるものが設けられていて、1~2週間は(さらに長く設ける学校もあるようですが)どちらを着てもいいですよ、ということになっているのですってね。ちょっと羨ましくなります。
きものの衣替えについては、すでにやりとりをした通り「場に応じて臨機応変に」ですが、何かと気を遣うお茶の世界などでは、学校のように「いついつからいついつまでは移行期間とする」などとお家元の公式見解を出してもらえたら、皆大変助かるのになあ、と思うのであります。公式見解に頼るのは情けないようですが…。
そんなつぶやきはさておき、本格的な衣替えを前に、先日単衣のきものを引き出しの底からひっぱり出しました。同時に、袷のきものを改めて点検し、メンテナンスに出すべきものは出すなどしてお手入れ――をしなくてはイケマセン。次の秋、また気持ちよく着られるようしておかなくては。
このあたり、わりと無精にしてきましたので、これを機に!と少し勉強しました。そして本職の方からもいろいろ教えていただいてきました。今日はまず、すごーく基本的なところからおさらいしていきたいと思います。
以下宿題のレポートみたいになってしまいました。興味のない方はスルーしてくださいね(笑)。だけど知っているようで意外に知らないことかも……なので、できればお付き合いのほど。
さて、そもそも衣類の汚れとはどんなものなのか!?というお話からはじめます。
汚れには、水溶性・油溶性・不溶性、という3つの性質があります。水溶性は文字通り水に溶ける汚れ、油溶性は油に溶ける汚れ。そして何にも溶けない不溶性の汚れは洗うのでなく「取り払う」必要があります。もう少し詳しくいうと…。
(1)水溶性の汚れ
たんぱく質、尿素、アンモニア、糖類、でん粉、塩分など。
例えば、汗、血液、ジュース、ワイン。
油に溶けにくく、水に溶けるから、水洗いが有効。
汗の成分のひとつ=たんぱく質は、そのまま放置しておくと黄ばみます。早めの水洗いが大切。

汗汚れは、黄ばんではじめて目に見えます。こちらは袷の着物の胴裏、脇まわり。見た目は真っ白だけど、霧吹きをしたら隠れた汗じみがくっきり浮き上がってきました。
(2)油溶性の汚れ
例えば、油脂、皮脂、食用油、化粧品(ファンデーションや口紅)、食べこぼし。
水に溶けにくく、油に溶けるから、ドライクリーニングが有効。
あるいは界面活性剤(石鹸であれ化合成洗剤であれ)を使った水洗いも有効です。界面活性剤は油汚れを包み込んで衣類から引き離し、水中に散らばせてくれます。


もっとも汚れやすいのは、袖口と襟もと。首と手首は特に清潔を心がけるべし。それでも汚れるのは避けがたいものです。
(3)不溶性の汚れ
例えば、ホコリ、土ぼこり、泥、錆、繊維くずなど。
不溶性の汚れは繊維のうえに「乗っかっている」イメージ。
水にも油にも溶けないから、何より日々の「ほこりとり」が有効。
水洗い、ドライクリーニングもある程度有効です。汚れが液中に流れるから。

裾まわりは土埃を集めがち。日々の「ほこりとり」が大事です。
というのが汚れの3つの分類。ただし殆どの汚れは単体でなく複合的なものなんですね。例えば汗(水溶性)と皮脂(油溶性)の汚れは同時に付きますし、食べこぼしには水も油も混ざりあってます。ここがお手入れの難しい部分です。
では、これらの汚れに対するお手入れというと、きものの場合(自分で水洗いができる綿や麻、洗えるきものは別として)、こんなステップがあると思います。
(1)日々着たあと ⇒点検&ほこりとり&陰干し
まずハンガーにかけて点検、そしてブラシでほこりとり。私は東京の平野刷毛製作所の「着物ブラシ」を数年愛用しています(といいつつ、毎回はやっていません・・・反省)。
陰干しの時間は2~3時間、長くて半日、なぜなら裾が袋になるなど型崩れの原因となるから、というふうによく言われます。
(ただし“皺を取る”という別の目的があるならば、2日ほど吊るしておくのもありなのでしょうね)
(2)日々積み重なる汚れ ⇒袖口・襟もと、汗抜き
「エリモト」などの溶剤を使った半襟のお手入れを紹介してくださいました。ほとんど同じ要領で袖口や襟もとのお手入れもできます。やり方は次回詳しくご紹介したいと思います。私は溶剤を使う量とか、スピード感、そのあたりがなかなか掴めないなあ、と常々思っていました。その疑問を解消すべく、プロのお手入れの様子をビデオに収めてまいりました。

なにやら慣れぬ手つきは、本職でなく私です。教えていただき、試行錯誤やってきました。
汗抜きについても自分でお手入れすることで、多少は汚れを軽減することができそうです。これも次回ご紹介するとして、プロの汗抜きはというと、こんなふう。
汗じみが見つかったところに霧吹きで水をふきかけます。すると布の下に隠れている吸い取り装置がみるみると、吹きかけた水を吸い取っていきます。こうして汗の成分が水に移って、きれいになります。
(3)部分的に汚してしまったら ⇒染み抜き
汚れの種類にもよりますが、染み抜きはやはりプロにお任せしたいところ。汚れによって、手を替え品を替え・・・ノウハウの蓄積があればこその世界です。大きな流れではベンジン⇒シンナー⇒水というふうに順番にテストしていくそうですが、とにかく技はたくさん。
ここで気になるのは汚してしまったときの「とっさの応急処置」です。水、血液、ソース、ワイン、インク・・・などなど様々な汚れがありますが、いずれにしても応急処置としてやっていいのは「水分を乾いたもので吸い取る」のみ。無理に吸い取ろうとすると、繊維の奥に汚れをますます浸透させることになるので、軽く押さえる程度。ついおしぼりなどが手元にあるととっさに使いたくなるのですが(実践済み・涙)、おしぼり厳禁です。そして吸い取る際は上から垂直にぽん、ぽん、とするのみに。押さえつけてはいけません。つい手に「ぎゅっ」とスナップがかかってしまうのですが、これもいけません。 何もしなければ水だけで綺麗に落ちたものが、おしぼりを使って押さえつけると、その後の処理に手こずり、染み抜き代が2倍3倍になってしまう…ということも少なくないそうですよ。
「水分を乾いた布で垂直に押さえるのみ。そしてすぐに染み抜きに。これ以外にして良くなることは一切ありません!」です。
(4)全体的に薄汚れてきたら ⇒丸洗い
丸洗いは、京洗い、生き洗いなどとも呼ばれますが、語感に反して、つまり“ドライクリーニング”。洋服のドライクリーニングとの本質的な違いはなく、扱い方が少々丁寧になる程度。溶剤には石油系のものが使われます。ただ乾燥のやり方には違いがあり、洋服の場合は乾燥機、きものの場合は自然乾燥、というのがオーソドックスなルールだそうです。
ドライクリーニングは、油溶性の汚れには強いけれど、水溶性の汚れを落とすことはできません。だから汗を多く吸っているものは別途汗抜きが必要。お手入れの業者によって料金体系は異なり、汗抜きも丸洗いに含まれている場合もあれば、別の場合もあります。チェックした上で“汗抜きが必要ですよ、つきましてはいくらいくら”と言ってくださる業者もあるし、チェックしない業者もあるかもしれません。いったん汗が変色してしまうと、それを消すのはかなり難しくなります。特に汗が気になるものは、確認しておいたほうがいいですね。
今回取材にご協力いただいた、京都のきものお手入れ処、松川調整所の丸洗いワークフローをご紹介すると、まず必ず汚れる部分をまっさらの溶剤で下洗い(具体的には襟まわり、袖口)したうえで、ドライクリーニング用の洗濯機で洗います。その際、溶剤のなかに洗剤や柔軟材を全く入れないのが特徴。ドライクリーニングの性質上、溶剤から洗剤を除去することはできず、必ず生地に洗剤の一部が残ってしまうのだそうです。下洗いをきちんとしていれば洗剤は必要ない、余計なものを残さないことが重要、との考えからこのようなやり方をされているそうです。溶剤を脱水したのちは自然乾燥。溶剤は完全に揮発するため、生地には何も残らないことになります。そしてふたたび検品、最後が仕上げ(アイロンがけ)、という流れ。


左=こちらがドライクリーニングの洗濯機。きものだからといって特別な機械を使うわけではありませんが、一般のクリーニングより小ぶりのものを使う場合が多いそう。こちらは10kgまで入る小さめタイプ。きもの1枚ずつネットに入れて10枚まで一緒に洗濯可能。右=溶剤を脱水したあとは、ハンガーにかけて自然乾燥。ドライクリーニングの溶剤は揮発性が高いのでほどなく乾きますが、半日はこの状態で完全に乾かします。
(5)すべてをさっぱりリセット ⇒洗い張り
洗い張りは最終手段かつ最良の手段。
きものを解いて、ごしごしと水や洗剤で洗います。ぴしっと伸ばして乾かします。布が蘇り、きものが蘇ります。ただ仕立てまですべて含めると数万円かかるわけですから、おいそれとはできませんね(自分でやっていた昔の人は偉大です)。


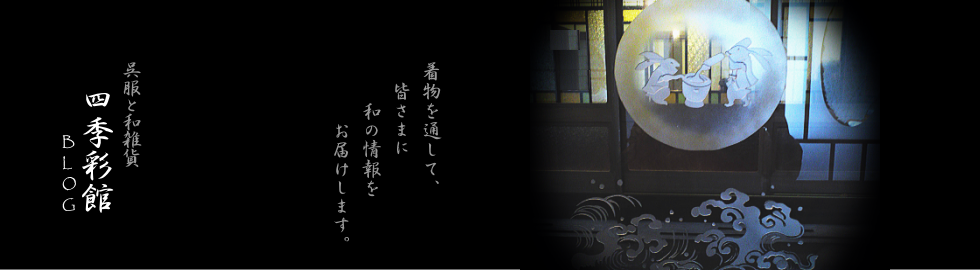
![200px-Long_stick_of_red_and_white_candy_sold_at_children's_festivals,chitose-ame,katori-city,japan[1]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/08/200px-Long_stick_of_red_and_white_candy_sold_at_childrens_festivalschitose-amekatori-cityjapan1-149x200.jpg)

![hurisodeobi2[1]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/07/hurisodeobi21.jpg)
![yjimage[5]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/07/yjimage5.jpg)
![1891096_422878537855573_107061540_n[1]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/07/1891096_422878537855573_107061540_n1-150x200.jpg)







![77443523[1]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/07/7744352311-225x300.jpg)

![775379up3[1]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/07/775379up31-199x300.jpg)
![76148447[1]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/07/761484471-300x224.jpg)
![91r959E82CD92N82AA928582E9[1]](http://www.shikisaikan.me/wp-content/uploads/2014/07/91r959E82CD92N82AA928582E91-192x200.png)



